

どこへ行っても、安くてうまいものは必ずある
というのが信ずるところ。
現地のフツーの人々が食べているもにこそ、うまいものがある。
でも本当は、味なんてどうだって構わないのだ。
人間はうまいものを食べるために、生きているのではない。
生きながらえているために食べているのだから。
たかがメシ……。されどメシ
カレー チェロケバブ ナスの煮物、魚サンド 芸者印の缶詰
インスタントラーメン フランスパン ピザ&食パン タコス
コーヒー ソパ・デ・マリスコス お総菜 ブラジル定食 シュラスコ クスクス
カレー
インド、ネパール、パキスタンでメシを食うとなると、やはりカレーになる。
「インドのカレーは目玉が飛び出るほど辛い」と思ってしまうが、私の経験では必ずしもそうではない。日本のカレー屋(例えば「ボルツ」)のカレーの方がずっと辛かったように思う。
基本的に庶民のメシ屋に入ると、ほとんどカレーしかなく、メニューもない。あるとすればチキン、マトン、野菜のバリエーションくらいで、値段もこの順番となる。
いくつかのスペースに仕切られたステンレスの大きな皿に、ゴハン・カレー・スープ(ダル)𠂉漬け物(アチャール)が並べられ、これがワンセットとなる。メインのゴハンとカレー以外のものは、お代わりできる。
ところによっては、メインのゴハンがチャパティだったり、ゴハンは最初盛られている一杯だけで、お代わりはチャパティのみというところもある。
ゴハンはいわゆる長細い米で、現地の男性は驚くほどたくさん食べるのだ。
初めは手で食べることに抵抗があるかも知れないが、慣れればこれが結構楽しい。食後、指をきれいにしゃぶったりするのが、快感になってきたりもする。熟練すれば、スープも指ですくって飲めるようにもなる。
もちろん使う手は右手だけで、左手はあくまでお尻を洗うためにとっておかなければならない。チャパティをちぎるときにも、左手を使わず右手だけでできるようになれば、それはもうインド流「粋」の世界なのだ。
チェロケバブ
ケバブというのは羊の肉のツクネ状のもので、チェロというのは米のこと。つまりゴハンの上に、串焼きの羊や焼いたトマトがのっているのがチェロケバブだ。
イランでは、飛び込みで入ったメシ屋で店これ以外のものを食べた記憶がない。戦争中だったという状況のせいもあったかもしれないが、地元に人聞くと「ゴハンは毎日食べているわけではない」とのこと。通常はパンを主食にしているらしかった。
パンはインドの「ナン」のように平たいワラジのようなもので、焼きたてはやはりうまい。ちなみに、この「ナン系」のパンはイランまでで、トルコに入ると普通のふっくらとしたパンが登場する。
ナスの煮物、魚のサンドイッチ
トルコに入ると急に食べ物が変わる。野菜の種類が、ぐっとバラエティに富んでくるような気がした。
食べ物に含まれる水分が増すとでもいえばいいのか、みずみずしくなってくるのだ。
トルコのメシ屋はロカンタと呼ばれているのだが、4〜5人掛けのテーブルの中央に、輪切りにされたフランスパンが山盛りに置かれている。客はケースの中に入ったおかずだけを注文して、テーブルに付く。つまりパンは食べ放題ということなのだ。
とにかく腹の減っていた私は、自然とパンのいっぱいあるテーブルを探すことになるのだ。
おかずはナスの煮物、豆の煮物、米の煮物(?)などで、味付けはトマトベースが多かった。これにパンを浸して食べれば、いくらでも食べられる。だから、パンの多いテーブルを選ぶ必要があるのだ。
イスタンブールでは魚が食べられる。
ガラタ橋の下にはシーフードレストランが軒を連ねており、怪しげな日本語を喋る、スーパマリオに似たオジサンたちが客引きをしている。もし、ザックにキッコーマンでも忍ばせていれば、心はすっかり日本の赤ノレンになってしまうのだ。
その近くの桟橋には、魚のサンドイッチを食わせる小舟がたくさん係留されており、なんと波に揺られる船の上で魚を油で揚げているのだ。
あれはアジだったろうか、揚げたての魚をフランスパンにはさんで売っている。これがシンプルだがうまいのだ。しかし、油が多すぎるのか、食べているうちに手が油でギトギトになる。すると手を洗いたくなるのが人の常。ふと、そばを見ると、水タンクを持ったオジサンが立っているではないか。
これが「手洗い屋さん」で、お金を払えば手を洗わせてくれるのだ。なんでも商売になるものだと感心してしまう。
そういえば、インドにはヘルスメーターひとつ置いて、道ばたに座っているオジサンがいた。金をとって客の体重を測るのだ。どこにでも、たくましい人間というのはいるものなのだ。
芸者印の缶詰
私にはヨーロッパのメシ屋について書き記す資格がない。
それは物価の高さに恐れののき、私のようなマネーレスの旅行者にはレストランで座ってメシを食うことができなかったからだ。それなら、どこで何を食っていたのかということになるのだが、ほとんど公園や駐車場で立ち食い、あるいはユースホステルで自炊をしていた。
自炊で重宝したのは、やはり米。当然、現地で買ったものだ。現地のスーパーで米が結構売られている。それも長細い米でなく、パールライスという日本の米とほぼ同じもので、しかも日本で買うよりもずっと安い。
おかずはハムやソーセージ、魚の缶詰など。魚の缶詰はUS$1くらいで買えた。なかでもオススメなのは、「GEISHA」という缶詰だ。芸者風のオネエサンの絵がブランドマークなので、多分日本製だろうと思ったのだが、定かではない。
トマトスープで煮たこのイワシの缶詰はよく食べた。もっと安いものに、モロッコ製のものがあったが、これは中にウロコが混じっていたりで、いまひとつだった。しかし、味には影響がない。
イギリスでよく見かけたのが、袋入りのインスタントラーメンだ。
日本製のものもあったと記憶するが、韓国製のものをよく食べた。これはまったく問題なく、私の貴重な食料源となった。
ラーメンの値段は、ピンからキリまであったが、安いものはどこの国の製造かわからない。試しに食ってみたが、油が良くなかったのか、気持ちが悪くなったものもある。
いろいろと試してみていただきたい。
フランスパン
食料のほとんどをスーパーで買って自炊し、イタリア料理もフランス料理も食べなかったのだが、ただひとつ自信をもってお勧めできるのが、フランスパンである。
これは文句なしにウマイと思った。やはり安くてウマイものは必ず存在するのだ。
日本でフランスパンと名の付くもの食べたことはあったが、フランスパンは固いというのが私の認識だった。ところが、フランスの小さな町のパン屋で買ったバゲットという種類のパンは実にうまかった。
パンの皮は確かに固い。しかし、その固さが違うのだ。日本にある薄焼き煎餅、いや、それよりももっと薄い皮が、中身を覆っているとでもいえばいいのだろうか、歯触りはまさにそれなのである。
それは、それまでに日本で食べたことのあるフランスパンとは、まったく別のものだった。
いつも2本ずつ買っていたのだが、そのうちの1本はあまりのうまさに、宿に着くまでに食べ尽くしてしまっていたほどだ。
ただし、一晩置くとパリッとした皮がフニャフニャになって、さすがに噛み切れなくなる。
それでも、日本のものとはまったく別物だと思っている。
ピザ&食パン
アメリカでも、ほとんどレストランでは食べていないが、自炊ができないときには、安くて腹にたまるものを食べていた。コストパフォーマンスからいうと、「ピザ」がベストだと思う。
ハンバーガーと比べても割安感があるし、一切れが結構大きい。これにソフトドリンクのMを付ければ、それなりの充実感はある。
しかし、どうしてもハンバーガーが食べたい人は、マクドナルドよりはバーガーキングのほうが腹持ちはいいような気がする。「メシは腹持ちの良さが勝負」なのだ。
キャンプをしていたときのメニューは、下のようなものだ。
𠂉朝食:食パン7〜8枚。うちマーガリン付き6枚、残りはジャム付き。コーヒー。
𠂉昼食:食パン7〜8枚。スニッカーズ1本。コーヒー。
𠂉夕飯:食パン7〜8枚。ラーメン1袋。ソーセージまたは缶詰。スニッカーズ1本。コーヒー。
ほぼ毎日これを通した。
毎日パンを一本買っていた。これがまた安いのだ。1本US$2弱くらいで買えた。前日に作ったヤツなどはUS$1もしないことがあり、これにはずいぶん助かった。
朝から食パン7〜8枚というのは異常だと思うが、とにかく腹が減って眠れぬ夜を過ごしており、朝は空腹で目が覚めるというキャンプ生活だった。
タコス&セビッチェ
メキシコは思ったほど物価が安くなく、おのずとタコスの世話になった。
とうもろこしの粉で作った、小型のお好み焼き版ような皮で、ソーセージや野菜を包んで食べるのだが、日本やアメリカのタコスとはやはり別物だという気がする。あんなに皮がパリパリしていない。
所詮ファーストフードなのだが、腹持ちはいまひとつだったという印象が強い。
「セビッチェ」は和食でいえば、「なます」と言うことになる。生の魚をレモン汁で和えたもので。これは日本人には結構うれしい味だ。
実のところ、メキシコに入った頃はスペイン語が一言もわからず、とにかく出されたものを食っていただけ。たとえそれがうまいものでも名前がわからず、残念ながら食べ物に関する印象があまりないのだ。
コーヒー
コーヒーは中南米にいればうまいのが飲める。
話によると、高級なコーヒー豆はすべて輸出向けで、その残りが庶民の口にはいるということだが、それでもうまかった。
別にカフェに入るでもなく、メシ屋でコーヒーと注文すれば、芳醇な香りのコーヒーが出てくる。特にコロンビアのコーヒーは、どんな場所で飲んでもうまかった。ただし、どこのコーヒーもかなりの量の砂糖が最初から入っていて、甘かったという記憶がある。クリームを入れる習慣はあまりないようだ。
メキシコではメシ屋のメニューにネスカフェというのがあり、それを注文するとホントにお湯とネスカフェの缶が出てきたことがあった。
ソパ𠂉デ𠂉マリスコス
チリというのは海産物の豊富なところで、「ソパ𠂉デ𠂉マリスコス」という海産物のスープが印象に残っている。これはエビ、イカ、貝、などが入ったスープで、トマトベースで仕上げているものが多かったが、実にうまかった。
私の場合、何を食べてもそれほどの感動はなかったのだが、このスープだけは妙に感動して食べた思い出がある。太平洋側の南端にあるプエルト𠂉モント近くに行けば、ウニや生ガキも食える。
お総菜
アルゼンチンでは肉が安く食える。現地ではチュラスコと呼んでいる。
アルゼンチンはヨーロッパの雰囲気が強く、レストランもキチンとしている(?)。つまり高い。となると写真のように、外でお総菜を買ってきてホテルで食べるということも多くなる。
写真:肉のフライとフライドポテト、ボリュームはたっぷりだ。右に見えるのは携帯の湯沸かし器。これがひとつあると便利だ。電気のコンセントに差し込むだけで、コップの水がすぐに沸騰する。
ブラジルの定食
ブラジルのドライブインで食事をしたときは、量の多さに驚いた。
どこにでも定食のようなメニューがあるのだが、試しに頼んでみるとなんと6〜7皿も出てくるのだ。サラダが数種類、スープ、肉類、さらにスパゲティやゴハンが一緒に出てくるのだ。
どこのドライブインでも内容は似たり寄ったりだが、量だけはどこも異常に多かった。残すのはくやしいので、なんとかクリアーしようと挑戦したが、一度も平らげることはできなかった。
今考えると、あれは一人前ではなく、何人かで食べるものではないかという気がしているが、確かなことはわからない。ご存知の人がいれば教えていただきたい。
シュラスコ
アルゼンチンではチュラスコと発音していたが、ブラジルではシュラスコと聞こえる。
本来肉のことを指すのだと思うが、これは料理の名前で、長いサーベルに突き刺して焼いたソーセージや焼き肉を食べるというものだ。
最近は東京でも、「シュラスコ食べ放題」といったビラを見かけるが、ブラジルではかなり高級な食べ物だ。私は知人に連れられてやっとありつくことができた。
いっぱい食べるコツ(?)は、最初にうちに出てくるソーセージなどをあせって食べ過ぎないことだ。メインの肉は後半に出てくるものらしいから。
クスクス
人を小馬鹿にしたような名前だが、歴とした食べ物だ。
アフリカが原産らしいがマルセーユあたりでも見かける。一見するとオカラのようにも見える。それが主食で、通常それにスープが付いて出てくるようだ。そのスープはトマトベースで、大根などの野菜が煮込まれている。
日本のおでんを思い起こすような味で、結構いける。
※私が実際にた食べたときの印象を多少の偏見を交えて書きました。
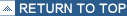
|