
オートバイ 装備 カメラ・フィルム
オートバイ
 ヤマハ・セロー(1回目) ヤマハ・セロー(1回目)
 1回目はヤマハ・セローの初期型(キックのみ)、2回目にはヤマハXT600のUS仕様を使った。 1回目はヤマハ・セローの初期型(キックのみ)、2回目にはヤマハXT600のUS仕様を使った。
セローは225ccで若干非力だったが、当時は中排気量のオフロード車が存在せず、なおかつ250ccのバイクはスピード追求で、すべてDOHCだった。自分で修理することなども考えて、SOHC(シングルカム)のセローいう結論に達した。改造は和光市にあるホワイトハウスに頼んだ。変更箇所はヘッドライトの交換、タンクの交換(初期型のテネレのもの)、キャリアの装着など。
荷物が重かったせいもあり、途中でエンジン非力さを痛感。特にドイツのアウトバーンでは、最高速は90km/hがせいぜいで危険さえ感じた。250cc前後の小排気量のオートバイに乗る他の日本人ツーリングライダーの話も聞いてみたが、エンジンを壊すのは先進国の良い道でのことが多いようだった。
 ヤマハ・XT600(2回目) ヤマハ・XT600(2回目)
 2回目はアメリカでを購入した。600ccにしたのは、非力なエンジンを全開で回すより、大きなエンジンをゆっくり回すほうがエンジンの寿命を長くなると考えたためだ。ただし、足つきは悪くなったのでその分立ちゴケも回数も増えたが、深刻な問題にはならなかった。 2回目はアメリカでを購入した。600ccにしたのは、非力なエンジンを全開で回すより、大きなエンジンをゆっくり回すほうがエンジンの寿命を長くなると考えたためだ。ただし、足つきは悪くなったのでその分立ちゴケも回数も増えたが、深刻な問題にはならなかった。
改造はなし。1回目のセローで特注のキャリアを付けたが、そのキャリアがあった安心感で荷物を増やしてしまったようなところがあった。その反省も含めて、「バイクはノーマル。荷物は少なく」をモットーにしてツーリングを行ったところ、それほど困ることはなかった。
旅のスタイルによるが、私を含めて日本人はどうも荷物をたくさん持つ傾向があるようだ。十二分に検討したほうがいいと思う。
パーツ
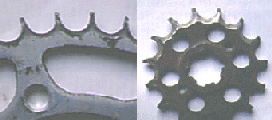 海外のツーリング、しかも長期間、なおかつ場所が第3世界ということになると、部品を持ちたくなるのが人情だと思う。国内のツーリングでは、周到な準備することが当たり前。それこそがちゃんとしたライダーの心得という感じだが、海外ツーリングでは必ずしもそうとはいえない。部品を持っていこうと思うと、限りなく増えるものなのだ。 海外のツーリング、しかも長期間、なおかつ場所が第3世界ということになると、部品を持ちたくなるのが人情だと思う。国内のツーリングでは、周到な準備することが当たり前。それこそがちゃんとしたライダーの心得という感じだが、海外ツーリングでは必ずしもそうとはいえない。部品を持っていこうと思うと、限りなく増えるものなのだ。
1回目はありとあらゆるもの(クラッチケース、ピストン、スプロケット、チェーンにいたるまで)を持っていったが、邪魔になることのほうが多かった。新品タイヤも2本持っていたが、それを載せて走るとなると楽しく走るどころではなくなる。快適に走れる荷物の重量は多くて20kg程度ではないかと思う。ましてや日本のオートバイは基本的によく走ってくれる。かさ張るものは極力避けるようにした方がよいだろう。
となると、走り初めのパーツの選び方が重要となる。少しくらい高くついても耐久性の高いものを選ぶべきだ。例えば、タイヤはグリップの良さを多少犠牲にしても、固くて減りの遅いものを選ぶ。チェーンは厚めのオイルシール入りを選ぶなどして長く大事に使うようにすれば、パーツは少なくて済む。
それでも何かの事情でパーツを交換しなければならないときは、現地で探すのだ。写真の前後スプロケットは、チリの首都サンチャゴで買ったものだ。
左のリアスプロケットはまったく別のバイクのものだが、取り付けの位置だけが合わなかったので加工してもらった。オートバイメーカーが眉をひそめそうな話だが、何とか走ることができた。パーツの少ないところでは、そのぶん加工技術が発達しているので「直して下さい」とお願いすれば、何とか助けてくれるものだ。
装備
 ヘルメット ヘルメット
1回目:GPA
2回目:ショウエイVTⅡ(?)
 オフロード用のフルフェイスが欲しかったのでGPAにしたが、結論としては私の頭に合わなかった。内装も帽体も日本製に比べると、ずいぶんお粗末な気がした。シールドも柔らかく、簡単に疵が付いてしまう。夕日に向かって走っていくときには結構辛かった。 オフロード用のフルフェイスが欲しかったのでGPAにしたが、結論としては私の頭に合わなかった。内装も帽体も日本製に比べると、ずいぶんお粗末な気がした。シールドも柔らかく、簡単に疵が付いてしまう。夕日に向かって走っていくときには結構辛かった。
2度目に使ったショウエイは相性が良かった。少し重かったが、かぶり心地は悪くなかった。オートバイ王国の日本人としては、オフロードバイクに乗るとき、ついオフロード用ヘルメットをかぶってしまうのだが、思い返してみるとオフロード用でなくとも良かったような気もする。要は雨や風や事故から守ってくれればいいわけだから、ロード用のフルフェイスでもいいのだ。
向かい風のなか、高速で走るときにはバイザーが妙に風を切って、首がカクカクとなるものだ。バイザーはなくとも良いのかも知れない。
 ブーツ ブーツ
1回目・2回目:クシタニ
 今もまだ売っているかどうかわからないが、ビブラム底で前面が赤い皮のブーツだ。このブーツは大変気に入っていた。2回目のツーリングの際にも同じ物を買ったほどだ。 今もまだ売っているかどうかわからないが、ビブラム底で前面が赤い皮のブーツだ。このブーツは大変気に入っていた。2回目のツーリングの際にも同じ物を買ったほどだ。
初めは少し皮が硬いが、直に足にフィットしてくる。フットペダル類の感触がわかりづらいが、それは慣れの問題だろう。何度か転倒して、足をバイクに挟まれたときも、ブーツの皮に少し疵が付いただけですんだ。堅牢さは十分だ。
ただ、快適なのはバイクに乗っているときの話で、これで歩き回るのはちょっと辛い。サブとしてスニーカーは必須となる。
 テント テント
1回目:ダンロップの冬季3~4人用+フライ
2回目:名前不明・フィリピン製
ダンロップは居住性は文句なしだが、バイクに積むにしては少しかさばるし重い。夏のアラスカは蚊やウンカなどの虫が多いのだが、どうもあの黄色を好むようで虫でテントの色が変わるくらいに寄ってきた。
もちろんモスキートネットが付いているので問題ないが、長く使っているとモスキートネットのジッパー近くの網目が綻んでくる。接着剤などで目止めをしつつ使用した。
フィリピン製テントは、2回目のツーリング、アフリカに上陸する前にパリで購入した物。これが噴飯物のテントで、ドーム型テントのポールがなんと竹でできていた。サハラを縦断するときに使用したが、砂嵐がこなくて良かったと思った。使用後3日目にその竹が割れ、ガムテープで補強して使った。それ以後、テントがイビツな形で立っていたのは言うまでもない。
 コンロ コンロ
1回目:GIストープ+オプティマス8R
2回目:オプティマス123
1回目は何故か予備のコンロまで持っていたが、さすがに8Rの方は途中で売ってしまった。
GIストーブは、レギュラーガソリンが使えるということで手元に残した。当然バイクのガソリンを併用するからだ。ただ、火力調節ができないのが難点。
2回目はホワイトガソリン用の123を使っていたが、レギュラーガソリンでもよく燃えた。そこでハタと考える。本当にホワイトガソリンというものが、必要なのだろうかと。
 バッグ バッグ
1回目:カリマー・ジョーブラウン+サカイヤ・3ウエイバッグ+ダッフルバッグ+ロウ・デイパック
2回目:サカイヤ・3ウエイバッグ+デイパック
バッグ類にはそれほど拘らなかった。ただ、バイクを降りたときに、背負っていけるようなタイプのものにした。サカイヤの3ウエイバッグは四角い形をしていて、オートバイに積むときには便利だった。このザックは1回目2回目と連続で使用した。上面がジッパーですべて開く形のもので、パッキング簡単だった。
ただ、このバッグに限らず、ジッパー全面開きタイプのものは、長い間使っていうちに、ジッパーが壊れて口がパックリ開いてしまう。そうなるとお手上げで、旅の後半は何とかジッパーをだましだまし閉じるというのが、毎朝の儀式となってしまった。
ジッパーが壊れた原因としては、荷物が重かったこと、砂埃が多いところを走ったこと、などいろいろ考えられるが、ジッパーの耐久性については、一度ジッパーメーカーの人にじっくり聞いてみたいと思っている。
 シュラフ シュラフ
1回目:羽毛・夏用
2回目:羽毛・冬季用(パリで購入)
シュラフに関しては、極力かさばらない物ということで、1回目は非常にコンパクトになる夏用の羽毛しか持っていかなかった。
ところが、カナダ、アラスカで使用したときは、正直なところ参ってしまった。8月の真夏なのに、日中でも5度Cくらいまでしか気温が上がらず、ホワイトホースについたときは、エマージェンシーブランケットをシュラフの中で巻いて寝た。それでも寒く、ウールの靴下とセーターを買ってやっと眠れるようになった。
寒いのには懲りたので、2回目アフリカに上陸する前は、パリでUS$250程度の冬用のシュラフを買った。これは今でも使っているが、まあまあだ。
カメラ・フィルム
 カメラ カメラ
1回目:ニコンFM2、ヤシカ(ベッピンレンズ付)
2回目:ニコンFM2、現場監督(レンズ切替なし)
カメラはメインとサブを用意した。選ぶときの条件は「電池がなくともシャッターが切れる一眼レフ」つまりマニュアルの一眼レフということだ。当時はオートフォーカスが台頭してきた頃で、マニュアルの一眼レフはキャノンF1とニコンFM2しかなかった。キャノンは少し値が張るし、重かった。自ずからニコンFM2を選び、標準のズーム(35mm~70mm)と200粍の望遠を持っていった。サブはヤシカのバカチョンカメラ。
ただし、それにはツアイスのレンズが付いていたので、他のバカチョンよりはずっといいだろうと思った。ストロボは持たなかった。夜ストロボ1発で撮る写真はヤシカで充分だろうと判断した。
結果的にニコンFM2は、グッドチョイスと思われた。カナダでカヌーを漕いでいたときに、湖に投げだされそのときにカメラも水没した。カメラの内部にまで水が入り、一時は「お先真っ暗」の状態に陥ったが、水がすっかり乾くと、奇跡的に動き始めた。露出計も含めての話だ。1回目のツーリングでは、最後までそのカメラで写真を撮り続けた。帰国後ニコンショップに持っていったが、そのときはさすがに修理不能で戻ってきたが、よくできたカメラだと思う。
2回目のツーリングに出発する前には、再び新しいFM2を買い、コンパクトカメラとしては現場監督を持っていった。その2台のカメラは、今も現役で活躍中である。
 フィルム フィルム
1回目:エクタクロームEN100・100本
2回目:コダクロームKR64・40本、エクタクロームEC100・40本
帰国後に印刷物にすることも考慮して、すべてカラーポジを持っていった。フジでなくコダックにしたのは、コダックのほうが発色がよいという盲目的な信仰があったためだ。今ではそんなこともないと聞くが、プロカメラマンには未だにこだわっている人も多いと聞く。
暑い国を通るので、感度の低いコダクロームKR64のほうが変化しにくいといわれたが、ISO64という感度であまり撮った経験がなく、カメラの露出計が動かなくなった場合にうまく撮れる自信がなかった。その点感度ISO100ならばなんとか行けそうだったので、あえてエクタクロームにした。撮影済みのフィルムをもってヨーロッパまでいったが、特に発色に問題はなかった。
ただ、10年たった今、その写真を見返してみると、退色して若干緑っぽくなってきているようだ。コダクロームで撮ったものは、退色がそれほどないような気がする。
フィルムを100本もつと、かさばるし結構重い。旅行中信頼できそうなラボを見つけたら、そこで現像をしてみてもよい。そのフィルムを航空便で日本に送れば荷物も減るし、留守を守っている人には手紙以上の連絡になることもある。ちなみに私はドイツで現像して、日本に送り返した。
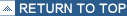
|